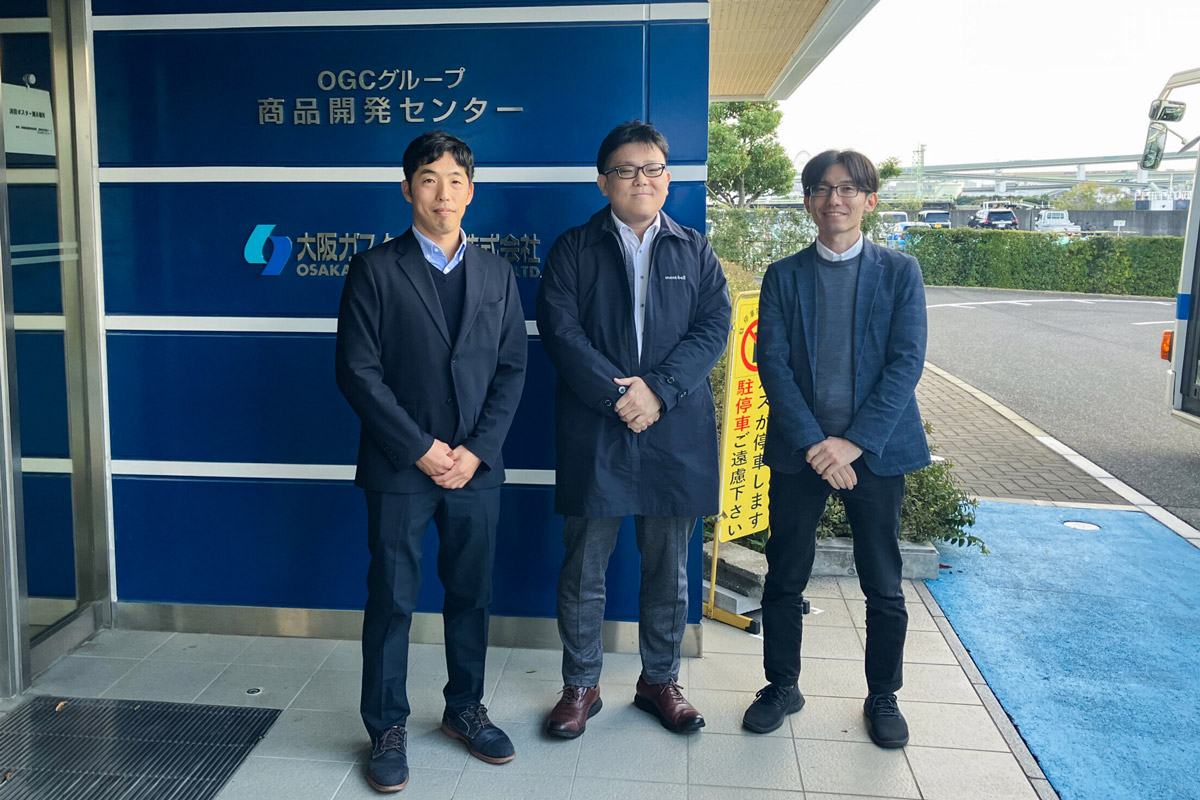今年で8回目!?ゴキブリが主役の企画展「ゴキブリ展8」でお話を聞いてきた
- 取材

Index
目次
Researcher

- 木村 健人
-
研究員 2009年入社
経営企画部webマーケティング課専任課長
シロアリ・木材腐朽菌に対する防蟻・防腐薬剤性能評価、木材保存について在学中に携わる。 2009年テオリアハウスクリニックに新卒入社。 数千件のシロアリ調査および駆除工事に従事。趣味はシロアリ飼育。
interviewシロアリの祖先がゴキブリであることを皆さんはご存知だろうか。
カサカサと動き、誰にも好かれず、家に出たら駆除されるあのゴキブリの仲間がシロアリなのだ。だが、防除業者としてシロアリには慣れ親しんでいる私たちであっても、ゴキブリについてはほとんど理解できていない。
ならばシロアリを理解する上で、その祖先でもあるゴキブリを理解しておくことが大切だろう。
そこで、今回は静岡県にある磐田市竜洋昆虫自然観察公園の企画展「ゴキブリ展8」にお邪魔してゴキブリストこと柳澤静磨さんにゴキブリのお話を伺ってきた。
※当記事には昆虫の写真を使用しております。苦手な方はご注意ください。
竜洋昆虫自然観察公園で開催中のゴキブリ展8とは?

今回、ゴキブリ展8へ取材に行ってきたのは、私と橋本、田中の3人。実は3人ともゴキブリを趣味で飼育しているため、ゴキブリには抵抗感があまりない。
本来であれば、ゴキブリが苦手なメンバーが1人くらいいたほうが良かったのかもしれないが、ここはより深い話を伺うためにも白蟻専科の精鋭を送り込んでみた。

田中
幼少期から現在に至るまで昆虫とともに育った昆虫エリート。飼育しているゴキブリはマダガスカルゴキブリのハバニカ。

橋本
同じく幼少期から現在に至るまで昆虫とともに育った昆虫エリート。飼育しているゴキブリはアルゼンチンモリゴキブリ。

木村
苦手だった昆虫を社会人になってから克服。
飼育しているゴキブリはマダガスカルゴキブリのポルテントーサ(ブラック)。
ところで、実は今ゴキブリがちょっとした話題になりつつある。
ゴキブリがニュースになったり、ゴキブリの企画展が様々な場所で実施されたり、ゴキブリが雑誌の袋閉じになっていたりするのだ。

その火付け役と言っても良いのが、今回お話を伺ったゴキブリ研究者の柳澤静磨さん。ゴキブリストという肩書でも活動されており、ここ数年で何種類もの新種ゴキブリを記載している凄い方だ。

柳澤静磨さん
磐田市竜洋昆虫自然観察公園副館長。大の苦手だったゴキブリの魅力に気づき、複数の新種のゴキブリを発表。ゴキブリストとして活動中。
磐田市竜洋昆虫自然観察公園で2月から3月末まで開催される「ゴキブリ展8」の企画者でもあるため、ゴキブリ展についても詳しく解説してもらった。

今日はゴキブリについて色々と教えて下さい…!

はい、今はゴキブリ展が開催されているので、まずは一通り展示しているゴキブリを見て回っていきましょう。

まず目につくのが入口の特等席に展示されているベニエリルリゴキブリとウスオビルリゴキブリ。これらは柳澤静磨さんの代名詞と言っても過言ではないゴキブリたちだ。

これはなかなか見ることができないルリゴキブリの仲間ですね。

このルリゴキブリって静磨さんが新種として発表された種類のゴキブリですよね?


そうですね、沖縄の離島の一部にだけ分布しているゴキブリで、こうやって発表しなければこの先もずっとひっそり暮らしていたであろう種類の子たちです。
先日、大阪の箕面公園昆虫館で筆者は標本を見ていた種類だが、生きている姿を見られるのは本当に貴重だ。ケースには生息地の様子を再現しつつ、観察しやすいように別容器に生体を入れて展示されていた。


現在では希少野生動植物種に指定されたので、生息地が荒らされることは無いと思いますが、ここで展示するゴキブリたちも貴重です。ストレスがかからないように展示するのが大前提なんですね。

にしても、こんなに綺麗なゴキブリがいることをほとんどの人が知らないと思うので、こうやって展示されていること自体がすごいですね…!


このヤマトゴキブリ、北海道も生息地に入ってますけど在来なんですか?

これは国内外来種ですね。本来は本州が生息域なんですが、植栽か何かで紛れ込んだのではないかと考えられています。

居ないはずの北海道にまで生息域が広がっているんですか…

ヤマトゴキブリは比較的寒い地域でも大丈夫なゴキブリなので、札幌の屋外でも生きることができるんですよね。
ちなみにこのヤマトゴキブリは北海道から逆輸入した個体とのことで、北海道のゴキブリを見たいというマニアックな方にもおすすめ。
ゴキブリとシロアリの関係についての展示も


シロアリの解説もしっかりありますね!

本当はこの一区画全部シロアリを置きたかったんですけど、置きたいものが多くて今回は1種類ですね。近縁のキゴキブリと一緒に並べようってことでケイバンキゴキブリの解説を付けています。
シロアリとゴキブリは近縁の昆虫だが、その中でもキゴキブリの仲間はシロアリに近いとされる。写真で紹介されているケイバンキゴキブリは韓国に生息するキゴキブリで、飼育が非常に難しく5℃程度の低温が適温なのだとか。

生体が展示されていたのはハワイシロアリ。レイビシロアリ科でアメリカカンザイシロアリの仲間だ。

そういえば、ゴキブリを観察していてシロアリっぽさを感じたりすることってありますか?

シロアリとゴキブリの似ているところ…ほとんどのゴキブリはそうは感じないですが、キゴキブリを飼育しているとシロアリっぽさもありますね。幼虫の形態だとか、一緒に端っこにまとまってるとか、そういうところとかは似ています。


幼虫はなんとなくシロアリっぽさがありますもんね。

シロアリとは結構離れたグループですけど、クチキゴキブリの幼虫なんかもシロアリにそっくり。頭が大きくて白っぽいので。

社内で飼育しているネバダオオシロアリの生殖虫は見た目にゴキブリっぽさを感じますし、お互いにやっぱり似ているところがあるのか…。

白蟻専科にて管理中のネバダオオシロアリ

あと、ゴキブリの採集をしているとシロアリってよく出てくるんです。そうすると、シロアリの巣の中にホラアナゴキブリという小さなゴキブリがいることもあるし、ゴキブリがゴキブリの住まいに入り込んでいる状態はおもしろいですね。

このケースの中に非常に小さなホラアナゴキブリがいる。白くてぱっとみた感じはシロアリのよう。

他にも、もともとシロアリへの寄生に起源がある冬虫夏草(※)がゴキブリに寄生するようになったクチキゴキブリタケが最近発見されたり、そういう意味で言えばゴキブリとシロアリは切り離せないんだな、って思います。
※冬虫夏草…昆虫類に寄生するキノコの一種。宿主の体内から菌糸を伸ばし子実体を作る。
いよいよゴキブリ展8メイン会場へ


ここがメイン会場です。まずはこの投票用紙を…。

実はこのゴキブリ展、毎年必ずGKB48という総選挙が実施されている。展示されているゴキブリ約60種の中から48種が選挙に選抜され、期間中の投票の結果から上位7ゴキブリに神7の称号が与えられる、という企画。

この取り組みをすることで、お客様がゴキブリ1種類1種類をじっくり見てくれるようになったんです。

確かに、投票用紙を貰うと推しを見つけなきゃって気分になっちゃいますね!

こちらが靴箱(投票箱)。企画展をじっくり見たあとに、推しの靴箱にこっそり入れれば投票完了だ。


昨年もGKB48の総選挙をしたので、今年の神7は専用ブースで展示してます。去年の1位はミドリバナナゴキブリでしたね。

毎年どれくらい投票されるんですか?

昨年は8000以上の票がはいりましたね。

え、そんなにたくさんの方がゴキブリの投票に来られるのか…


結構遠くからも来てくださる方が多くて、去年は台湾からもわざわざ見に来ていただいた方もいらっしゃいましたよ。
と、神7の解説をしていただいてるところで手のひらに取り出してくれたのが巨大ゴキブリの「ヨロイモグラゴキブリ」。


このヨロイモグラゴキブリは丈夫なのでイベントに必ず持っていくゴキブリなんですよね。この子も6年くらい経っていますけど、ずっと元気でいてくれてます。皆さんも持ってみます?


かわいい…


かわいい…

重量感があって、動きもゆっくりでほんとにかわいい…飼いたくなってしまいますね

僕も皆さんから飼育するゴキブリのおすすめを聞かれますけど、必ずヨロイモグラゴキブリをおすすめしますね。ゴキブリの飼育で1番の問題は脱走なんですが、このゴキブリは開けてても脱走する心配がないのですごく良いと思ってます。

確かに、ゴキブリが脱走したら大惨事…


このヤエヤママダラゴキブリはずっと水の中にいるんですか?

このゴキブリは結構特殊で、幼虫のころは危険を察知すると水に潜って隠れる習性をもっているんですよね。観察したときは10分くらい水に入っていることもあったので、気門が外に出ていれば長時間入っていられるみたいです。


しかもこのゴキブリ、成虫が大きくて格好いいですね…

成虫は日本最大のサイズなので、現地でみるとすごく大きいですね。夜行性で葉に付いていたりするんですが、取ろうとすると暴れ狂ったように動くので、やっぱ日本最大でもゴキブリはゴキブリだなって…

すべては解説しきれないが、とにかく「はじめまして」のゴキブリたちばかりで多様性に富んでいる。ゴキブリといえば黒くてすばしっこい嫌な奴、というイメージが、多くの人にとって覆されるのは間違いないだろう。
ちなみに、チャバネゴキブリやクロゴキブリ、ワモンゴキブリといった私達に馴染み深いゴキブリたちも、飼育ゲージで囲われたここなら安心して観察できるため存分に見ておきたい。
2階の会場にはゴキブリコレクションが


2階にはゴキブリに関するグッズや資料を展示しています。これは世界各地のごきぶりホイホイですね。


これは面白いですね…!やっぱりどこの国でもゴキブリは嫌われ者…

南アフリカでは薬剤を使わない点が強調されてるみたいだし、ゴキブリの写真がそのまま使われているのも日本では考えられないかも。

国や地域によってはゴキブリだけでなくて、サソリやヤモリが対象になっているのも、その国や地域ごとのニーズが見えて面白いんですよね。

個人的に面白かったのが、ゴキブリの名前の由来。もともと、御器(お椀)にかぶり付く虫ということから「ごきかぶり」と呼ばれていたものが誤記載で「ゴキブリ」になったそうだ。意味を知っていれば少しはイメージが変わるかも。

他にも、ゴキブリの琥珀や化石など、静磨さんが収集したゴキブリコレクションが展示されていた。白蟻専科にもシロアリの琥珀が欲しい…。
非公開のゴキブリ飼育部屋へ


ここは普段非公開のゴキブリ飼育部屋です。

すごい…壁一面のゲージ、これ全部ゴキブリですか…?

そうですね。累代で飼育しているゴキブリたちを約100種類飼育しています。展示しているのが50種類ちょっとなので、半数はこのバックヤードで管理しているんです。

すごい…

展示にもいましたけど、ヒメマルゴキブリも乗せてみます?


さっきのヨロイモグラゴキブリとはまた違うかわいさ…

これはこれでいいね

ヒメマルゴキブリのメスはダンゴムシのように丸まる習性があるゴキブリで、見た目もゴキブリよりもダンゴムシにしか見えないんです。

これならゴキブリが苦手な人でも大丈夫そうですね。オスも同じように丸まるんですか?

ええと、オスは羽があって見た目はゴキブリなんですよね。

そうなんですね…


これはブラベルスクラニファーというゴキブリなんですが、捕まえて匂いかぐと干し椎茸の匂いがするんですよ。


ほんとに干し椎茸のにおいがする…。

次はこれでラーメン作れるじゃないですか。

この飼育部屋では展示のためのゴキブリだけでなく、研究のために管理されているゴキブリたちも多くいる。この先もここから新たな成果が発表されていくのだろうと思うと感慨深い。
ゴキブリ展について静磨さんが思うこと

今日はゴキブリ展の解説をしていただきありがとうございました…!すごく勉強になったのですが、静磨さんはそもそもなぜゴキブリ展を始めようと思われたんですか?

昔から昆虫が好きなのにゴキブリのことをあまり知らなかったんですよね。ゴキブリって嫌われているけど、昆虫好きな自分でさえ深く知らなくて。

自分でも知らないってことは、他の人はもっと知らないだろうなと。ゴキブリの多様性を見せつつ展示という形にしたら興味を持ってくれるかな、と思ったのが大きいですね。


実は当園では以前からクロゴキブリの生体を展示していて、それを見たお客様の反応がすごく良いことは知ってたんです。 昆虫を展示していると、反応の良い虫、悪い虫がでてくるんですよね。クロゴキブリについては、事務所にいても分かるくらいお客様の反応があって。実はみんなゴキブリが好きなんじゃないかって何となく感じていました。

今回のキャッチコピーも、「キモイキモイも好きのうち」ですもんね。

ですね。そういうところから始まったのがこのゴキブリ展です。


それじゃあ、最初にゴキブリに興味を持ったキッカケは何かあったんですか?

昆虫公園では年に1回、研修があるんですよね。最初は西表島だったんですが、そこでヒメマルゴキブリを見つけて、それが丸くなった瞬間に「こんなゴキブリもいるんだ」と。そこから興味を持ちましたね。


マダラゴキブリは水に潜るし、ホラアナゴキブリはすごく小さいし、そもそも卵の産み方も違う。そういう多様性に魅せられて…

気づいたらクロゴキブリも・・・?

そうですね…笑 あと、単純に昆虫の中で段違いに飼いやすいんです。取ってきたまま飼えて繁殖もできる。昆虫館は飼育して展示する施設ですから昆虫館向きの昆虫かな、と。

確かに、ゴキブリは簡単に増えるイメージがありますね。

あと、クワガタやカブトムシに引けを取らないくらい有名な昆虫じゃないですか。皆さんも、ゴキブリ展ってどんなものか想像しやすいと思うんです。例えば、ダルマガムシ展だと「何?」となってしまうじゃないですか。ゴキブリならみんなが知っていますから、展示との相性は良かったですよね。


ゴキブリって聞けば誰でも知っている虫ですもんね。ちなみに、今回の企画展で見てほしいポイントって何かありますか?

この規模でゴキブリの生体を展示しているのは世界でもうちだけだと思うんですよね。標本にすると色も変わるし体長もかわってしまうので、生きたままの彼らを見られるというのは、1番の見どころかなと思います。


確かに、自分の人生でこんな多くのゴキブリを見られるとは考えもしなかったです…。これだけ貴重な企画ですし、やっぱり沢山の方に見て欲しいですよね。

知らないままゴキブリ嫌いな人がほとんどだと思うので、知ったうえで嫌いか、そうでもないか、好きになるか、まずはその一歩を踏み出してくれると嬉しいですね。


じゃあ来年も再来年も…?

継続って実は難しいけど、とても重要だと思います。最初に1回やると話題にはなりますが、1回で終わってはあまり意味がないですからね。

ぜひこのまま毎年続けてほしい企画展だと思います。できればシロアリも…笑

そうですね…!シロアリはまだ飼育の部分がネックですけど、いずれ企画してみたいです。
ゴキブリ展8は2025年2月1日から3月30日【追記】4月13日まで延長開催中だ。知っているようで全く知らないゴキブリの世界に足を踏み入れて、あなたも彼らの多様さと面白さを体感してみてはいかがだろうか。
ゴキブリ展8の概要
期間:2025年2月1日(土)〜4月13日(日)
場所:磐田市昆虫自然観察公園
詳細はホームページから
Related
関連記事
view all